


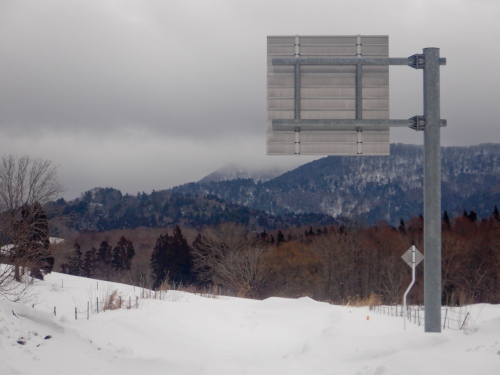


| 2025 冬景色の海を眺めて適当に東北旅 〜津軽沿岸・津軽海峡・陸奥湾沿岸〜 2月3日(月) | 林道探索の書 〜今日もどこかで林道ざんまい〜 |
| 4日目 | 外ヶ浜町→ むつ市「湯野川温泉 岡村旅館 yunokawa onsen okamuraryokan」 | もどる |
 |
 |
 |
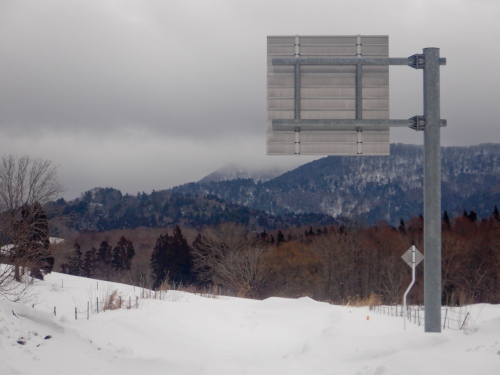 |
 |
 |
| [ トップへもどる ][ 1日目 ][ 2日目 ][ 3日目 ][ 4日目[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]へ ] |
 |
|
スノーシェッドを抜けた先も一面雪まみれでしたが、野平では道沿いに風力発電用の小型風車を見かけました。でも野平に風力発電所はないはず。
|
 |
|
住民はダム建設によて全員が集団移転しましたが、農業的には移転先から通いで現在も続けられている野平。しかし、さすがに全てが雪に埋もれる冬は無人状態となり、見渡す限りの雪原に人の気配は微塵も感じられなかったです。
|
 |
|
雪まみれで誰もおらず通りがかる車も皆無でしたが、ここが野平の中心地。ここでも県道沿いに点在する風力発電用の小型風車が見えていますが、あの風車は風力発電投資用の「土地付き分譲小型風力発電」らしいです。 なお、小型風力発電の売電価格は、2017(平成29)年までは24時間の発電量が20kW未満の小型風力発電は[ 55円 / kWh ]だったのが、同年以降は20kW以上の買取価格と一本化されたことで2025(令和7)年時点で[ 11円 / kWh ]にまで大暴落。 しかし、野平の風力発電については、過去に資源エネルギー庁による固定価格買取制度の認定を受けているため、現在も買取価格55円 / kWhが維持された高利回り物件らしいですが、すでに販売は終了しているのでそのつもりでね。 |
 |
|
公共交通機関は通っておらず、最寄りの集落からも遠くて冬は隔絶の地となる野平。道すがらには寒々とした雪景色が広がり、実際、寒くてたまらないのですが、山々の峰を覆い尽くす鉛色の雪雲を目にすると、なんだか気が滅入ってくるなぁ・・・。
|
 |
|
そんな感じでガチガチに凍結した県道を進んで行くと、やがて行き先表示板の掲げられた十字となった交差点が見えてきます。
|
 |
|
ちなみに秋の季節の野平はこんな感じ。前方に青い行き先表示板が掲げられた交差点が見えていますが、10月になると木々が一斉に色づき始め、どこもかしこも燃えるような紅葉で埋め尽くされます。
|
 |
|
県253の終点になっていて、脇野沢から大間に向かう通称「海峡ライン」ことR338に接続する交差点です。脇野沢からR338を通ってくれば、仏ヶ浦までの距離は川内町経由よりも格段に近いのですが、しかし、生憎と脇野沢〜野平間は冬季閉鎖中。この季節は川内町経由で向かうしかありません。 なお、「福浦」と記された右折方向は野平〜福浦間を結ぶ野平林道になっていますが、野平林道のダートはとうに全滅して全線舗装済み。それでも野平から佐井に行く場合の便利な近道なのですが、生憎こちらも冬季閉鎖中。 |
 |
|
交差点の傍には集団移転で放棄された野平集落の家屋が・・・。崩れかけた牛舎とサイロが見えますが、雪に埋もれた姿が痛々しかったです。
|
 |
|
交差点の左折側は海峡ラインの脇野沢方向ですが、こちらは冬季閉鎖中。除雪されていないので道路は深い雪に埋もれていますなぁ。ちなみにこの交差点から脇野沢までは海峡ライン経由でおよそ25km。それが川内町経由だと45kmくらい。
|
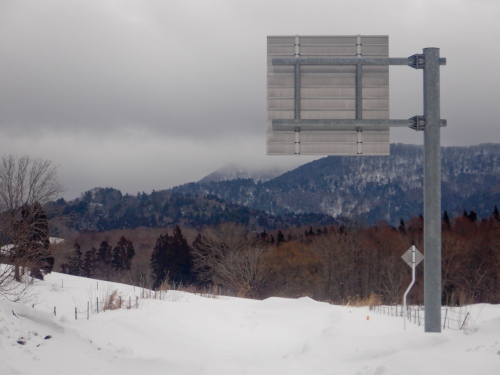 |
|
深い雪で閉ざされた海峡ラインの脇野沢方向。脇野沢から「人切山(458.8m)」や「湯ノ沢岳(557.5m)」、「アンド山(6458.6m)」の山間を縫って野平へと至る海峡ライン(R338)は、かつて「牛滝越」と呼ばれ、江戸時代の書物で「深山幽谷九曲折坂」と表現されるほどの難所だったそうです。
|
 |
|
牛滝越の道筋は海峡ライン開通以前の地図にも、山道を示す点線で道筋が記されていたそうですが、現実には獣道程度の道しかなかったとのこと。建設工事は難所続きで自衛隊の協力も得て行われたんだよな〜。
|
 |
|
そして1978(昭和53)年10月16日、待望の「県道大間脇野沢川内線(海峡ライン / 現R338)」が開通したというわけ。当初はダート県道状態で開通した海峡ラインですが、現在の国道へと昇格されたのは1982(昭和57)年8月のことでした。
|
 |
|
こちらは冬季閉鎖中の海峡ラインの脇野沢側からだと直進となる野平林道方向。左折側の佐井(R338)、右折側の畑(県253)方向は除雪されていますが、福浦へと至る野平林道方は放ったらかしで深い雪に埋もれて冬季閉鎖中だったです。
|
 |
|
というわけで県253の終点であるR338との交差点は佐井方向への直進一択しかないので直進しますが、すぐに電光掲示板が現れました。え〜となになに?
|
 |
|
うむ。R338(海峡ライン)の野平〜脇野沢間が冬季閉鎖中であることを示す電光掲示板ですが、観光客のいない真冬の季節に脇野沢から海峡ライン経由で野平や佐井方面に向かう地元車なんてまずいねーし、当然かな。
|
 |
|
野平から佐井村に入って真冬の海峡ラインを進んでいきますが、やがて「牛滝川」伝いに緩く下っていきます。しかし、仏ヶ浦まではひたすら山深い山中を巡るコースが続いて海は全く見えていなかったです。
|
 |
|
途中、牛滝川の深く切れ込んだ谷間を見下ろせる地点がありますが、この牛滝川の谷間伝いに下っていくと、佐井村「牛滝」集落があります。牛滝は下北半島南西部の九艘泊〜佐井間にかけて、断崖絶壁が続いて集落がほとんどない海岸沿いにある数少ない海辺の集落。一度訪れてみたいと思っていた場所なんだよな。
|
 |
|
なだらかにくだりつつさらに進んでいくと、仏ヶ浦を目指して山中をゆく国道から海岸へと下り、牛滝へと至る分かれ道の入口が現れますが、かつて牛滝越と呼ばれたのは、脇野沢からこの先の牛滝までの区間です。
|
 |
|
ちなみに牛滝入口は下北半島を一周するときに必ず通りががる地点。下北半島をツーリングしたことのある方ならば高確率で通りがかっているはずですが、ほとんどのライダーはわざわざ牛滝に立ち寄ることなく仏ヶ浦を目指すので、ここ牛滝入口については記憶が無い方がほとんどでしょう。
|
 |
|
いつの間にか雪がちらつき始めてしまった牛滝川の谷間。この谷間伝いに1kmほど下った牛滝川の河口に牛滝集落があるはず。海上、陸上ともに公共交通機関はなにも通じておらず、九艘泊よりも僻地度は高くて下北半島の中でも訪れにくい場所ですが、それをさらに訪れにくい真冬の季節に訪れちゃおうというわけ!
|
 |
|
海峡ライン(R338)から左折して牛滝川伝いに下っていくと、やがて放置された網や小舟、漁具小屋などが現れて漁村チックな雰囲気が漂ってきます。
|
 |
|
通りを歩く人の姿もなくてひっそりと静まり返った牛滝の家並みメインストリートを進んでいきます。牛滝川河口に位置し、西は津軽海峡に面して対岸に津軽半島、北西に松前半島を望む牛滝は村としての歴史は古く、寛文年間(1661〜)の頃からすでに津軽海峡を行き交う船の寄港地になっていたとのことのこと。
|
 |
|
牛滝川沿いの僅かな平地に民家が連なる集落を進んでいくと、河口に架かる橋を渡った先に牛滝漁港がありました。漁港は小さな湾を防波堤で仕切った内側にあり、小雪混じりで吹き付ける風が猛烈に冷たかったですが、ちょっと散策してみます。
|
 |
|
牛滝漁港を示す看板ですが、牛滝は港としての歴史も古くて、1699(元禄12)年、当地を支配していた南部藩によって川内湊、佐井湊と共に「田名部七湊」に指定され、蝦夷地、西廻り、東廻り航路の寄港地になっています。
|
 |
|
牛滝川の河口に設けられた牛滝漁港の北側、すなわち漁港がある湾の右手は砂浜っぽくなっていて、漁の小舟が雑然と並べられていました。また、浜には重機が数台留め置かれてなにかの工事が行われていたようですが、海水がとてもきれいです。
|
 |
|
牛滝川の河口です。こんな感じで牛滝川が注ぐ河口は小さな湾になっていて、その左半分が牛滝漁港になっています。湾漁港のある湾を取り囲む断崖は北は仏ヶ浦の遥か先の佐井まで、南は九艘泊まで途切れることなく続いているため、海峡ラインが完成する以前の牛滝はまさに陸の孤島だったんだよな〜。 そのような地理的条件もあってか、150年ほど昔の藩政時代の牛滝は九艘泊と同じく、南部藩の「遠追放六ヵ所」の1つにされていたりもします。 |
 |
|
なんだか隔絶感が物凄く感じられて最果てムードが濃厚であった牛滝漁港。人っ子一人誰もいない冬の漁港の雰囲気が心に染み入りますが、それでも牛滝はかつて海の流通の要所として賑わった場所。 江戸時代には塩も生産し、特産物は意外にも「椎茸」だったという牛滝。その牛滝からは主にヒノキ材が積み出され、廻船問屋が大いに儲かったとのこと。1738(元文3)年の「田名部海辺問屋定」には牛滝の廻船問屋として坂井義兵衛、大関清左衛門、田中彦兵衛、能登屋善兵衛さんら4人の名が記されています。 ちなみに青森〜佐井間(脇野沢、牛滝、福浦寄港)にはシイラインの「ポーラスター」が所要時間2時間30分で1日2往復(冬季は1日1往復)運行していましたが、残念ながら2023(令和5)3月31日で廃止。この定期船の廃止によって牛滝に通う公共交通機関は全滅。運転免許を持たぬ者には訪れるのが困難な場所になりました。 また、牛滝漁港からは牛滝〜仏ヶ浦間にグラスボートの観光船「夢の海中号」が往復1000円で1日2往復季節運行されていましたが、こちらも時を同じくして2023(令和5)年に運行終了。訪れた時は牛滝漁港の片隅に使われなくなった観光船が放置されていましたが、朽ちゆく古ぼけた観光船がの姿が痛々しかったなぁ・・・。 |
 |
|
漁港のすぐ外は津軽海峡。およそ40km離れた渡島半島は見えていませんでしたが、津軽海峡に面した牛滝は海峡警備にはちょうど良い場所だったらしく、1793(寛政5)年に「船遠見番所」が設けられ、1808(文化5)年には大砲が2挺備えられ、さらには嘉永(1848〜)の頃には台場が築かれています。
|
 |
|
牛滝漁港から振り返って牛滝川上流方向を眺めるとこんな感じ。川筋に牛滝の民家が連なっているのが見えていますが、牛滝に唯一あった旅館は廃業してしまい、今は郵便局と酒屋、牛滝診療所と佐井村立牛滝小中学校があるだけ・・・。 ちなみに村立牛滝小中学校は本州では唯一の「へき地5級校」。2021(令和3)年度から児童生徒数がゼロになって休校されていましたが、2023(令和5)年に再開されたのが牛滝での近年まれにみる明るいニュース。 2023(令和5)年に転入希望者が現れたこと、また、2026年に牛滝生まれの男児が就学することを受けて、それまで廃校ではなくて休校とされていたのが前倒しで再開されたんですね。ただし、2023(令和5)年に再開されたのは牛滝小中学校のうち牛滝小学校のみ。牛滝中学校については2025 (令和7)年4月から開始されています。 |
 |
|
1963(昭和38)年頃の牛滝の様子。2025(令和7)年現在、牛滝小中学校には小学生1名と中学生1名しかいませんが、この頃はまだ子供も多くて牛滝小学校の児童数はなんと58名も! 村の通りでも普通に子供の姿を見かけたそうです。 ただし、当時はまだ海峡ラインは完成されておらず、そのため牛滝の住民は買い物は25kmも離れた隣村まで歩いて泊まりがけで行っていたんだって。 |
 |
|
漁港からしばし海を眺めたら牛滝を出発しますが、今は小さな酒屋が1軒あってその前に自販機があるだけで淋しい限りであった牛滝。 隣の福浦集落までは13km、脇野沢までは30km、最寄りのGSがある佐井までは30km、一番近いスーパーがある川内までは31km。できればこのような最果ての漁村の鄙びた宿で旅の一夜を過ごしたかったのですが、しかし、牛滝の旅館はすでに廃業しているし、立ち去るしかねえやなぁ・・・。 なお、これは余談ですが、1727(享保12)年頃の牛滝には「牛滝川目金山」が存在していたらしいです。金山は現在村立牛滝小中学校が立っている「牛滝川目(うしたきかわめ)」と呼ばれる辺りで稼働していたといわれますが、なにぶん300年も昔の話。伝説っぽくもあり、詳しい記録は残されておらず詳細は不明・・・。 |
| [ トップへもどる ][ 1日目 ][ 2日目 ][ 3日目 ][ 4日目[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]へ ] |